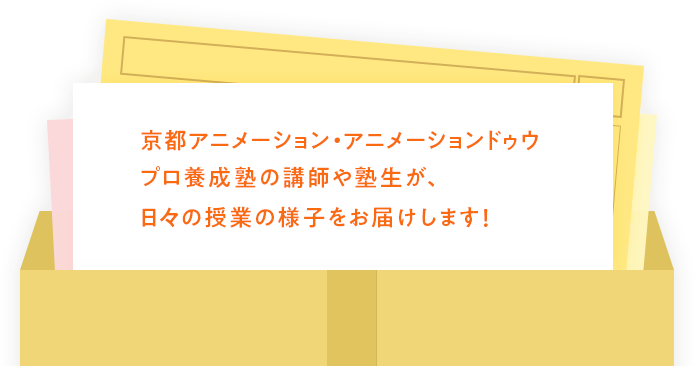2025.10.31
プロ養成所に通い始めてそろそろ半年がたちます。
今までの人生で一番充実していた半年で、あっという間の時間でした。
現在、私は『レイアウトから原画まで』の課題に取り組んでいます。
レイアウト作業では絵コンテの意図を読み取り、読み取ったものを反映しながら形にするという能力が求められます。
私は大学で4年間学んでいましたが、レイアウトについては絵コンテの絵を綺麗に正確に描きおこすというような漠然とした理解しかありませんでした。
プロ養成塾の授業では『絵コンテの絵を描きおこす』のではなく、『絵コンテから画面のイメージを読み取り、形にする』作業なのだと教わり、目から鱗が落ちる思いです。
形にするうえでパースや画角の知識が必要になり自分の力不足を感じるのはもちろんですが、『イメージを読み取る』という段階から躓く事も多く、いかに自分が『イメージ』という最初の部分を疎かにしてしまっていたかを痛感しています。
このような技術面以外の部分でも、根気強くご指導いただける環境にいられることはとても貴重で、凄くありがたい経験だと感じています。
この課題に限らず、プロ養成塾に入ってからは自分が気がついていなかった弱点を本当に沢山教えて頂き、力不足を感じながらも向き合うべき課題がハッキリ見えているということへの喜びを実感しています。
残り半年、焦る思いもありますが課題の一つ一つに真剣に向き合い、4月からの半年よりも充実した日々になるように頑張りたいと思います。